シンエイ通信【令和7年2月1日作成 182号】
シンエイ通信【令和7年2月1日作成 182号】

◇九州木材商況
九州・沖縄8県の11月の新設着工戸数は合計7739戸で前年同月比0.5%増だった。
持ち家は沖縄以外の7県で増加したが、賃貸住宅は福岡、熊本以外で減少した。今年は4号特例縮小など法改正が控えており、3月までは駆け込み需要の影響もあるとみられているが、4月以降の住宅受注の減少が予想される。特に6月以降は本格的に住宅着工数が減少し、製品の荷動きや全体的な仕事量が減少するとの見方が強く、先行きが不安視される。
そのため、川上から川下まで非住宅に注力していく方針だ。プレカット工場は非住宅の受注を強化しており、原木市場関係者は行政や他社と協力し地域材を集荷するなど大型物件に対応した取り組みの重要性を指摘する。
今年に入り製品の荷動きは好調だが、メーカーは長らく続く原木高製品安により採算性が悪化している。業界の新年会では業界全体で国産材製品価格を上昇させることの必要性を訴える声も聞かれた。出材量は回復傾向にあるものの積雪などの影響はみられた。伐採届の手続きが厳格化されていることも慢性的な出材減少に関係している。昨年末に高騰していた桧は高止まり。
【国産構造材】
値上げが課題
年明け以降製品の荷動きは昨年12月と比較すると好調だが、羽柄材より構造材の方が荷動きは鈍い。原木価格が長らく高値を維持していることから製品の値上げ交渉を行っているメーカーもあるものの、それが通るまでには至っていない。
一方、流通関係者からは若干値上がりの雰囲気があるとの声も聞かれた。
製材メーカーの採算性は悪化しており、現状の荷動きが今後も続くかどうかは見通しづらい。製材メーカー関係者がらは「耐える一年なりそうだ」との話が複数聞かれた。製品価格は横ばい。
【国産羽柄材】
荷動きは順調
荷動きは順調だが、丸太高製品安のため先行きは不安視されている。前年に続きローコスト住宅向けなどでB品の引き合いが強い。採算性を向上させるため、メーカーは羽柄材も構造材同様価格を上昇させたい意向だが、製品価格はほぼ横ばい。
木材以外の価格が上昇するなか製品のみ弱含んできたことが問題視されている。今後も住宅着工の減少は続く見通しのため、いずれ荷動きが鈍くなった際も価格の下落を防ぐことが鍵となるという。
【外材】
横架材に動き堅調
米松平角、欧州材構造用集成材の荷動きは堅調。建築基準法改正前の駆け込み需要が主因とみられ、年明けも引き合いが落ちておらず、スポット需要がでている。春以降の住宅需要は懸念されるが、供給面からの需給引き締まりが注視される。
外材羽柄・小割材は、産地価格の上昇などで先高観が強まっている。一方、国産材製品もKD材は消費地向け出荷が増え、手当しづらくなっている。
【集成材】
入荷コスト上昇の見通し
欧州材の2025年第1・四半期契約の交渉は、Wウッド及びRウッド構造用集成材は、前回の24年第4・四半期契約分から全体的に約20ユーロ程度値上がりした。為替を交渉中の1ユーロ162円~164円でみると横ばい、今後円高に振れない限り、春先の輸入コストは前回成約分より1段高になる見通しだ。
日本国内の構造用集成材の荷動きは、昨年10月をピークに緩やかに下降線をたどっている。ただ、輸入構造用集成材の入荷が同月以降低水準で推移しているため、港頭・市中在庫に品薄感が出てきた。
プレカット工場の在庫は必要量が確保されているが、予定外の手当てをすると価格は相場より一段高となり、特にWウッド集成管柱は手に入りにくいといわれている。
【合板・建材】
在庫補充の動き
建築基準改正前の駆け込み需要などからプレカット工場の稼働率は回復しており、流通業者を含めて針葉樹構造用合板を在庫補充する動き。価格は横ばい。他地域で安値からの底打ち、反発が見られるなか、安定した荷・値動きになっている。
厚物合板への引き合いも増えてきた。省エネ基準義務化への対応、非住宅木造建築向けなどで一定量の需要が出ている。
輸入型枠用合板は入荷量が多少回復してきたが、円安傾向でコスト高は変わらず、価格は居所高のまま。供給の安定した国産合板を活用する動きも進んでいる。内装材は住宅向けが低調だが、商業施設やスポーツ施設向けなどは堅調だ。
◇緊急輸送道、進む耐震化 無電柱化は遅れ目立つ―阪神大震災30年

災害時の避難や救助、物資輸送では、円滑な道路交通が欠かせない。阪神・淡路大震災をきっかけに選定が始まった「緊急輸送道路」の耐震化が進み、地震への備えが強化された。一方で、道路の閉塞(へいそく)を防止するための無電柱化は遅れが目立ち、国土交通省は対策を急いでいる。
阪神大震災では、被災地の道路交通がまひした。阪神高速3号神戸線では橋脚が折れ、635メートルにわたって横倒しになり、並行する国道に崩れ落ちた。阪神高速では落橋も発生し、被害箇所全ての復旧に約1年8カ月を要した。こうした状況により、救助活動や物資輸送が停滞した。
震災の教訓から、国交省は緊急輸送道の優先的な耐震化に着手。高速道路や国道、これらの道路をまたぐ道路橋を含め、落橋・倒壊の防止対策に取り組み、2021年度までにおおむね完了した。さらに、道路に段差が生じて通行に支障を来すような被害の軽減に向けた耐震補強も進めている。
他方、急務なのが無電柱化だ。国交省は、電線の埋没工事に当たる自治体を財政面などから支援。市街地にある緊急輸送道の約2万キロで優先的に対策を講じている。ただ、事業着手率は23年度末時点で約45%にとどまる。25年度までに52%へ引き上げるのが目標だ。
無電柱化が難しい要因として、市街地ほど水道管やガス管など既に地中に埋まっている物が多く、関係者との合意形成に時間がかかることが挙げられる。交通量が多いところでは、作業時間が深夜や早朝に限られるといった難しさもある。費用の高さもネックで、国交省調査では、埋設による無電柱化の場合、1キロ当たり約5.3億円に上る。
国交省担当者は現状について「スピード感に課題がある」と指摘。コスト削減や工期短縮につながる技術開発を推進するとともに、緊急輸送道には電柱の新設を認めないといった規制策も講じて、対策の加速化を図る。
このほか、道路が損傷したり、樹木などでふさがったりする事態も想定し、早期復旧に向けた備えも進めている。国交省出先機関の地方整備局と各都道府県は24年中に、復旧作業の優先箇所や事業者の役割分担、必要な機材の保管場所を盛り込んだ「道路啓開計画」の策定を完了。地元建設事業者を交えた机上演習や訓練も展開する。

無電柱化のイメージ
阪神大地震で横倒しになった阪神高速3号神戸線=1995年1月、神戸市東灘区(阪神高速提供)
◇米国年間150万戸割れか?住宅ローン高止まり
2024年12月の米国新設住宅着工は、年率149万9000戸(前月比15.8%増、前年同月比4.4%減)となった。
月間では集合住宅を中心に好調だったものの、24年の着工数は22年以来2年ぶり150万戸を割る可能性もある。
24年11月の改定値は年率129万4000戸で、速報地を若干上方修正した。
内訳は、戸建て住宅が105万戸・集合住宅41万8000戸と11月からは大幅に伸長したが、23年12月の値には及ばなかった。建築許可件数は、年率148万3000戸とやや低水準。内訳は、戸建て住宅が99万2000戸、集合住宅は43万7000戸だった。
米国の30年固定住宅ローン金利は、24年12月中は6%後半で推移し、25年1月には24年5月依頼となる7%を超えた。1月中旬は8%近くまで上昇している。
米国の中央銀行にあたる連邦準備制度理事会はインフォレーション抑制のため政策金利を下げる回数を減らしたことから、住宅ローン金利もしばらく下がらないとの見方が出ている。新築住宅価格の上昇傾向も続いている。
一般的には住宅市場の回復には5%を下回る必要があるとされるが、日本の木材業界では「移民が多く住宅需要がある」「中古住宅も高く売れる」との理由で、25年の住宅着工数は伸びるとの見方も多い。
20日に新しくトランプ大統領が就任し、住宅向け施策等が注目される。
◇リサイクル石膏100%の「チヨダサーキュラーせっこうボード」厚9.5mm品
チヨダウーテは、リサイクル石膏を100%使用し、製造時の実質カーボンニュートラルを実現した「チヨダサーキュラーせっこうボード」に厚さ9.5mm品をラインアップした。
同社はトクヤマと共同で、廃石膏ボードを収集してリサイクルするトクヤマ・チヨダジプサムを2011年に設立し、2013年から廃石膏ボードのリサイクル事業を開始。
2023年6月には、廃石膏ボード由来の原料石膏を100%使用した「チヨダサーキュラーせっこうボード」の販売を始め、引き合いが増えているという。
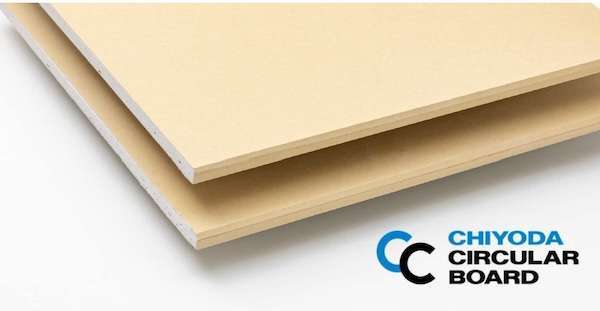
今回は、同製品のラインアップに厚さ9.5mm品が加わった。
910×1820×9.5mm。準不燃材料。
設計価格1400円/枚
◇Z世代 住宅ローン35年超 「フラット50」2.6倍、月学負担を重視
Z世代の価値観が返済まで35年以内という住宅ローンの常識を変えつつある。一定の条件を満たす住宅を対象に最長50年まで融資する「フラット50」は30歳未満の2024年の申請数が719件と、前年の2.6倍になった。住宅価格の高騰に加え、趣味なども重視するZ世代ならではの考え方が背景にある。
「マイホームを持ちつつ月々の返済額を抑えたい若年層のニーズと、多少のリスクを負っても長く利息を取りたい金融機関の思惑が一致した」ライフルホームズ総研の中山チーフアナリストはこう話す。
フラット50は、国が定めた基準を満たす長期優良住宅を対象に固定金利で最長50年まで融資する商品だ。
住宅金融支援機構によると、世代別の利用割合は30歳未満が4割弱で、30代に続いて2番目に多い。
持ち家志向強くフラット50の利用者の増加は、最長35年まで融資する「フラット35」との金利差が縮小したことが主因だが、変動金利型でも若年層を中心に超長期の住宅ローンが伸びているという。
「住宅も金利も上がっている。「よい物件が見つかればすぐ購入したいと考えている」こう話すのは埼玉県吉川市で大和ハウス工業の建売住宅を購入した28歳の男性だ。
24年7月に期間40年の変動型のローンを契約し、9月から月11万円返済している。以前住んでいた社宅の家賃は月4万円だったが、駐車場料金や勤務先の住宅手当を配慮すれば月々の実質負担はほぼ変わらない。若者の持ち家志向は強まっている。総務省の23年の家計調査によると、世帯主の年齢が29歳以下の2人以上世帯の持ち家率は23年に35.2%と、過去最高となった。この男性は「賃貸を契約し続けることも考えたが、高齢になるにつれ審査が通りづらくなる不安があった」と明かす
趣味も諦めない賃貸から持ち家に移った後も可処分所得を一定程度確保し、余裕のある生活を送りたいというニーズも強い。2件前に埼玉県桶川市で三井ホームの戸建て住宅を購入した29歳の男性は40年ローンを契約した。月々の返済額は13万円で、35年で組むよりも月額1万円~2万円程度抑えられる。
「趣味の旅行やテニスにも十分にお金を使える上限額が付き13万円だった。生活コストを圧縮してまで借入期間を短くする選択肢はなかった。」こうした需要にこたえる様に最長50年の住宅ローンの取り扱いは増えている。23年に住信SBIネット銀行がネット銀初めて取り扱いを始め24年に楽天銀行も提供し始めた。
地銀でも、もともと普及している九州・沖縄に加え、東北でも広がりをみせているという。
金融機関にとっても利点がある。住宅ローンは金融商品のかなでも借り倒し率が比較的低い。借入期間が長いほど利ざやを稼げる余地が生まれ、顧客との接点も長期に及ぶ。
40年ローンを契約した男性2人に共通するのは「所得の一部を投資信託などで運用し、成果が出れば繰り上げ返済の原資にする」との考え方だ。足元の生活にゆとりを持たせ、市況に合わせてライフプランを変えていくZ世代は、長く返し続けなければならず、返済総額も増える住宅ローンに対して柔軟な姿勢でいる。